「まさか自分の店で…」
飲食店オーナーであれば、誰しもがそう思うでしょう。しかし、どんなに衛生管理を徹底していても、食中毒のリスクを完全にゼロにすることはできません。もし、不幸にもあなたの店で食中毒が発生してしまった場合、その初期対応がお店の存続を大きく左右します。
適切な対応を迅速に行うことは、お客様の健康被害を最小限に食い止め、風評被害を抑制し、最悪の事態である倒産を回避するための唯一の道と言えるでしょう。
この記事では、飲食店で食中毒が発生した場合に、オーナーが取るべき9つのステップを解説します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
食中毒発生時の第一報と対応
まず、食中毒が発生した場合、症状が現れたお客様からの連絡や、従業員への通報が初動となります。食中毒は通常、症状が発現してから数時間から数日以内に現れます。お客様やスタッフが下痢や嘔吐、腹痛、発熱などの症状を訴えた場合、以下の手順を踏んで対応します。
症状の確認と記録
- お客様の具体的な症状(吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱など)を詳しく聞き取り、発症時間、摂取した食事の内容、同席者の有無などを丁寧に記録します。
- 可能であれば、体調不良者の連絡先(氏名、電話番号、住所)を確認しておきましょう。
お客様の状態への配慮
- お客様の不安な気持ちに寄り添い、謝罪の言葉を述べ、状況を丁寧に説明します。
- 必要に応じて、医療機関への受診を勧め、救急車の手配や病院への付き添いなど、できる限りのサポートを提供します。
- 他のお客様への情報提供も適切に行い、不必要な混乱を避けるように努めます。
従業員の健康状態の確認
- 他の従業員や、同時刻に食事をした他の顧客に同様の症状が出ていないかを確認します。
- 嘔吐や下痢などの症状がある従業員は、直ちに業務から外し、隔離し、医療機関を受診させます。
食材の特定と提供停止、保全
食中毒の原因となった可能性のある食材や料理を特定し、二次的な被害を防ぐための措置を講じます。
疑わしい食材・料理の特定
体調不良を訴えたお客様が摂取したメニュー、使用した食材、調理時間などを詳しく調査します。同じ食材や料理を摂取した他の顧客や従業員の状況も参考に、疑わしいものを絞り込みます。
食中毒が疑われる料理を絞り込むことができたら、提供を一時的に中止します。その後、食中毒が正式に確認されるまで営業を停止することが推奨されます。
当該食材・料理の提供停止
原因が特定されるまでは、疑わしい食材や料理の提供を直ちに中止します。
まだ提供していない分は廃棄、または他の食材と明確に区別して保管します。
食中毒が正式に確認されるまで営業を停止することが推奨されます。
残存食材・調理品の保全
疑わしい食材の残ったもの、調理途中のもの、調理済みの料理のサンプルなどを、汚染されないように密封し、冷蔵または冷凍保存します。
これらのサンプルは、後日保健所や検査機関による調査の重要な手がかりとなります。
購入時の納品書や伝票なども保管しておきましょう。
保健所への迅速な連絡と情報提供
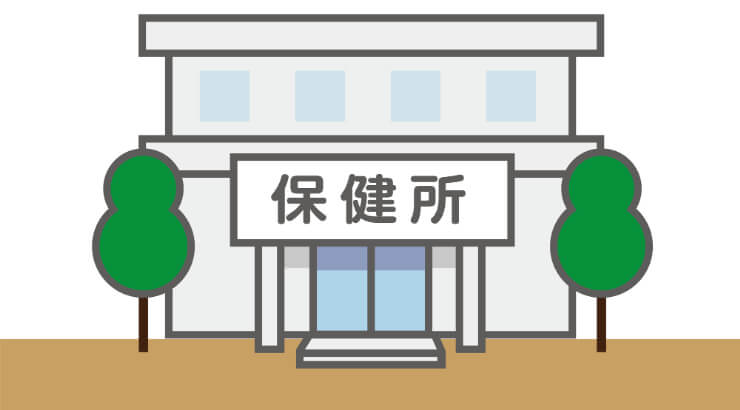
食中毒が発生した場合、速やかに最寄りの保健所に連絡することが義務付けられています。
保健所への報告義務
食中毒が発生した疑いがある旨を伝え、発生日時、場所(店舗名、所在地)、患者数(疑いを含む)、主な症状、推定される原因などを簡潔に報告します。保健所の指示を仰ぎ、今後の対応について確認します。
詳細な情報提供
保健所の調査に協力し、以下の情報を提供します。
- 患者の氏名、連絡先、症状、発症日時、摂取した食事の内容、同席者の有無など
- 疑わしい食材の仕入れ先、購入日、保管状況、調理方法、調理担当者など
- 店舗の衛生管理体制、過去の衛生指導履歴など
- 保全している食材・調理品のサンプル
保健所の指示遵守
保健所の指導に従い、原因究明のための調査や、感染拡大防止のための措置(営業自粛、消毒など)を適切に実施します。
お客様への誠実な説明と謝罪、情報共有
体調不良を訴えたお客様や、来店を予定していたお客様に対して、誠実に対応することが信頼回復の第一歩です。
当該のお客様への連絡と状況説明
- 体調不良を訴えたお客様に改めて連絡を取り、症状の経過などを確認します。
- 食中毒の可能性について正直に伝え、謝罪の意を表明します。
- 今後の調査状況や、お店としての対応について丁寧に説明します。
他のお客様への情報提供
- 店舗のウェブサイトやSNS、店頭告知などを通じて、食中毒発生の可能性と、現在調査中である旨を公表します。
- 予約のキャンセルや変更などが発生する可能性があるため、該当するお客様には個別にも連絡を取ります。
- 不安を感じているお客様からの問い合わせには、誠意をもって対応します。
原因究明のための徹底的な調査と事実確認
保健所の調査に協力するとともに、店舗内でも独自に原因究明のための調査を行います。
従業員への聞き取り調査
当日の調理担当者、食材管理担当者、提供担当者など、関係する従業員全員に、食材の取り扱い、調理方法、衛生管理状況などについて詳細な聞き取り調査を行います。些細なことでも見逃さず、記録に残しましょう。
衛生管理記録の確認
日々の衛生管理チェックシート、食材の温度管理記録、調理温度記録などを確認し、不備や異常がなかったかを検証します。
作業手順の見直し
- 店内の衛生状態や厨房の清掃状況を再点検します。交差汚染や手洗いが不十分でないか、確認することが重要です。
- 食材の仕入れ、保管、下処理、調理、提供といった各工程における作業手順に問題がなかったかを改めて見直します。
- マニュアルとの乖離や、不適切な点がないかを確認します。
類似事例の調査
過去に同様の事例が発生していないか、他の店舗で同様の食中毒が発生していないかなどを調査します。
食品衛生管理体制の見直しと再発防止策の策定・実施
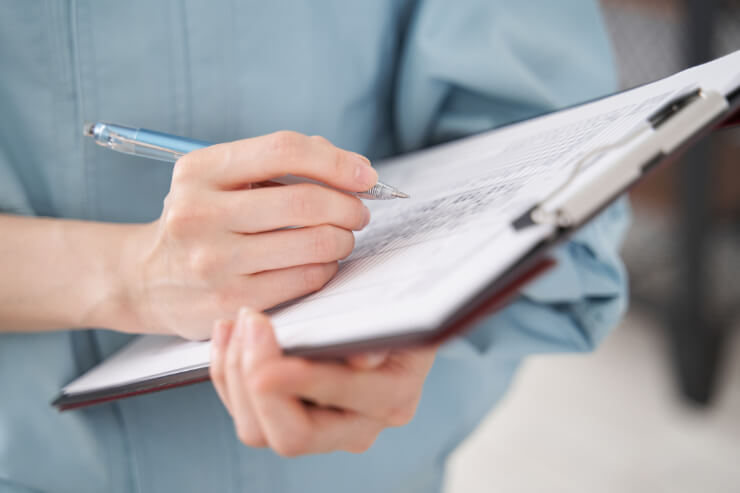
食中毒の発生を防ぐためには、発生後にどれだけ迅速に対応できたかだけでなく、再発を防ぐための取り組みも欠かせません。食中毒を未然に防ぐための具体的な対策を講じることが、店の信用を回復し、長期的な経営を安定させるために重要です。
原因が特定されたら、二度と食中毒を発生させないための具体的な再発防止策を策定し、実行に移します。
原因に応じた対策の実施
加熱不足が原因であれば加熱方法の見直しと徹底、温度管理の不備が原因であれば管理方法の強化、従業員の衛生知識不足が原因であれば教育の徹底など、特定された原因に応じた具体的な対策を講じます。
食材を仕入れる際には、信頼できる業者から購入し、保存方法や期限を徹底的に管理します。また、食材の取り扱い時に異常がないかチェックし、異常を見つけた場合には使用しないようにします。
衛生管理マニュアルの改訂
必要に応じて、衛生管理マニュアルを見直し、より具体的で実行可能な内容に修正します。
新たな対策や手順を盛り込み、全従業員に周知徹底します。
従業員への再教育と意識向上
食中毒の予防には、従業員の衛生意識が重要です。食中毒の発生原因と再発防止策について、全従業員に対して改めて教育を行います。
手洗いの重要性、衛生的な作業手順、体調不良時の報告義務などを徹底的に指導し、衛生意識の向上を図ります。
定期的なチェック体制の構築
再発防止策が確実に実行されているか、衛生管理体制に緩みがないかを定期的にチェックする体制を構築します。チェックリストの作成や、責任者の明確化などが有効です。
汚染された可能性のある食材の廃棄、調理器具・店内環境の徹底的な消毒

二次感染を防ぐために、汚染された可能性のあるものや場所を徹底的に処理します。
疑わしい食材の廃棄
保健所の指示に従い、原因となった可能性のある食材や、汚染された可能性のある食材を適切に廃棄します。
調理器具・設備の徹底消毒
疑わしい食材に使用した調理器具、食器、作業台、冷蔵庫などを、適切な消毒剤(次亜塩素酸ナトリウムなど)を使用して徹底的に消毒します。消毒後は、清潔な状態で保管します。
店内環境の消毒
嘔吐物や下痢便が付着した場所はもちろん、お客様や従業員が触れる可能性のあるドアノブ、テーブル、椅子なども、消毒剤で丁寧に拭き上げます。必要に応じて、専門業者による消毒を依頼することも検討します。
お客様への補償と信頼回復への努力
食中毒によってお客様に迷惑をかけたことに対する誠意ある対応は、信頼回復のために不可欠です。
謝罪の実施
食中毒が発生した場合、迅速にお客様に謝罪します。お詫びの言葉とともに、状況や原因、再発防止策を説明し、誠実に対応することが大切です。
補償の提供
食中毒によりお客様が被害を受けた場合、適切な補償を提供することが重要です。医療費の負担や後遺症がある場合には、必要な手続きに協力します。お客様の状況に合わせて、お見舞いの品を持参したり、改めて謝罪の意を伝えたりするなど、丁寧な対応を心がけます。
保険会社への連絡
食中毒は補償の対象外ですが、保険会社によっては特約を付帯することで補償を受けることもできます。飲食店向けの賠償責任保険に加入しておくと安心です。
メディア対応と風評被害対策
食中毒に関する情報は、瞬く間に広がる可能性があります。適切なメディア対応と風評被害対策が重要となります。
保健所との連携
メディアへの情報発信は、必ず保健所と連携を取り、正確な情報に基づいた対応を心がけます。
誠実な情報公開
事実に基づいた情報を隠蔽することなく公開し、誠意ある姿勢を示すことが重要です。
憶測や不確かな情報の発信は避け、混乱を招かないように注意します。
信頼回復に向けた継続的な努力
再発防止策の実施状況や、日々の衛生管理への取り組みなどを積極的に発信し、お客様の信頼回復に向けて継続的に努力します。
まとめ
飲食店で食中毒が発生した場合の対応は、一連の迅速かつ適切な行動が求められます。初期対応の遅れや誤った対応は、お客様の健康被害を拡大させるだけでなく、お店の存続をも脅かしかねません。
万が一の事態に備えておくことが、飲食店オーナーにとって最も重要な責務と言えるでしょう。日々の衛生管理を徹底することはもちろん、発生時の適切な対応を確立することで、お客様の安全を守り、お店の信頼を維持し、未来へと繋げていきましょう。
#飲食店 #食中毒 #対応 #初期対応 #再発防止


























